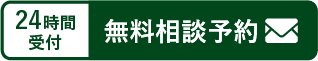トラック5台は本当に必要?運送業許可の「最低車両台数」ルールを行政書士が徹底解説

運送事業の立ち上げを志すあなたが、まず最初に耳にするルール、それが「トラックは最低5台必要」という要件でしょう。
正直なところ、「本当に5台も必要なのか」「初期投資が大きすぎる」と感じる方も多いのではないでしょうか。
特に創業期においては、この「5台」という数字が、あなたの前に立ちはだかる大きな壁のように見えるかもしれません。
しかし、声を大にしてお伝えしたいのは、この「5台ルール」は事業を成功させるための重要な土台です。
この数字の裏に隠された、法律の真意と、見過ごすと起こりうる最も重いリスクを、専門家として分かりやすく解説します。
1. なぜ「5台以上」と法律は定めているのか?
運送業の許可要件は、単に「規制」として存在するわけではありません。「なぜ」このルールが必要なのかを深く掘り下げると、その背景には「国民生活の安全と安定」という、極めて真剣な目的があるのです。
安定した事業運営を国が求める理由
トラックが1台や2台では、どうなるでしょうか。もし事故や故障が発生した瞬間、荷主様との約束を果たすことができず、たちまち事業継続が困難になってしまいます。運送業は、日本の経済や物流を支える公共性の高い事業です。
国(国土交通省)は、個人事業の片手間ではなく、安定した輸送サービスを継続的に供給できる体制であることを求めています。
5台以上の車両と、それに見合ったドライバーを確保すること。これは、「事業」として成り立つための最低限の規模なのです。
最も重いリスク:「無理な運行」と「安全の崩壊」
車両台数が少ない場合、その少ない車両とドライバーに過度な負担がかかることは避けられません。
- 過労運転の誘発: 車両が少ないと、修理や点検の間に業務を回すため、ドライバーが無理な長時間労働を強いられやすくなります。
- 整備不良のリスク: 定期的な整備・点検を十分に行えず、重大な事故につながる整備不良のリスクが高まります。
5台という数字は、これらの悲劇を防ぎ、安全管理体制を組む上での最低ラインとして考えられているのです。
2. 知っておくべき「5台ルール」の例外規定
原則は5台ですが、地域や輸送品目によっては例外が認められています。あなたの事業計画が以下の例外に該当するかどうかを確認してください。
- 5台以下で申請が可能な特例(国土交通省の定める基準による)
- 霊柩運送
- 一般廃棄物運送
- 一般的に需要の少ないと認められる島しょの地域における事業
- 【注意】 ここでいう「島しょの地域」とは、本土や他の地域と橋梁による連絡が不可能な島に限定されます。橋で繋がっている島は、原則としてこの例外には該当しません。
3. 5台の車両、すべて「購入」する必要はないのです
「5台すべて自己資金で買う必要がある」と誤解されている方も多いのですが、答えはノーです。
法律が求めているのは、トラックを「使用する権限」があることです。「所有」である必要はありません。
自己所有とリースの比較
| 区分 | メリット | デメリット |
| 自己所有 | 資産になる、最終的なコストは安い場合がある | 初期投資が非常に大きい |
| リース | 初期費用を大幅に抑えられる、車両管理の手間が少ない | 月々のリース料が発生する、契約期間が概ね1年以上必要 |
運送業の許可申請においては、リース会社との長期契約(概ね1年以上)を結んだ車両でも全く問題なく認められます。
購入とリースを組み合わせることも有効な手段です。ご自身の資金計画と照らし合わせて、最適な方法を選択することが重要です。
4. 許可を阻む落とし穴:車検証の「名義」
車両の要件で、申請者が最も引っかかりやすい「穴」が、車検証の名義です。ここを見落とすと、他の要件が完璧でも許可は下りません。
- 絶対条件:車検証の使用者欄
- 最終的に、車検証の「使用者」の欄は、許可を申請する法人(会社)名義になっている必要があります。
なぜ名義が重要なのか?
運送業の許可は「会社(法人)」に対して下りるものです。会社が事業に使うトラックについて、「会社自身が使う権限を証明できること」が必須条件なのです。
申請者が「株式会社〇〇」なのに、車検証の使用者欄が「社長の個人名義」になっている。このままでは申請には使えないのです。
もし現在、社長個人の名義になっている場合は、会社名義に変更する手続きが必要になりますので、注意してください。
5. 5台の「数え方」で間違えやすいポイント
「5台」をカウントする際にも、いくつか注意すべきルールがあります。
- カウント対象外となる車両
- いわゆる軽トラック(黒ナンバー)は、この「5台」には含めることができません。
- カウント対象となる車両の種別
- 主に1ナンバー(普通貨物)や4ナンバー(小型貨物)といった、事業用自動車として認められる車両です。
- 牽引車と被牽引車のカウント方法
- トラクター(牽引車)とトレーラー(被牽引車)は、セットで1両としてカウントされます。
- トラクターが5台あっても、トレーラーが5台なければ「5両」とは認められませんので、許可申請の際の資金計画時にはご注意ください。
最後に
5台という数字は、単なる行政上の手続きではなく、あなたの運送事業が「社会に対して安全と安定を約束できるか」を証明するための、いわば「信頼の証明書」です。
車両計画は、資金計画とも密接に絡み合う、事業の根幹です。もし、車両の準備や名義変更、資金調達など、許可取得に向けて迷うことがあれば、必ず専門家にご相談ください。
運送事業が、安全かつ着実にスタートできるよう、全力でサポートいたします。
引用元・参考情報
- 国土交通省:
- 一般貨物自動車運送事業の許可要件について、営業所ごとに配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上であること、霊きゅう運送等を除く特例があることが示されています。
- 普通トラックを使用して行う運送業 – 近畿運輸局
- 全日本トラック協会:
- 貨物自動車運送事業法ハンドブック等において、営業所ごとの最低車両台数(5台)の原則と、霊柩、一般廃棄物、島しょ等の例外について記載されています。
- 貨物自動車運送事業法ハンドブック
動画での解説はこちら
執筆:行政書士法人あゆみ 松本 亜由美