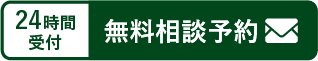トラック0台で運送業界に参入する!「貨物利用運送事業(水屋)」という選択肢
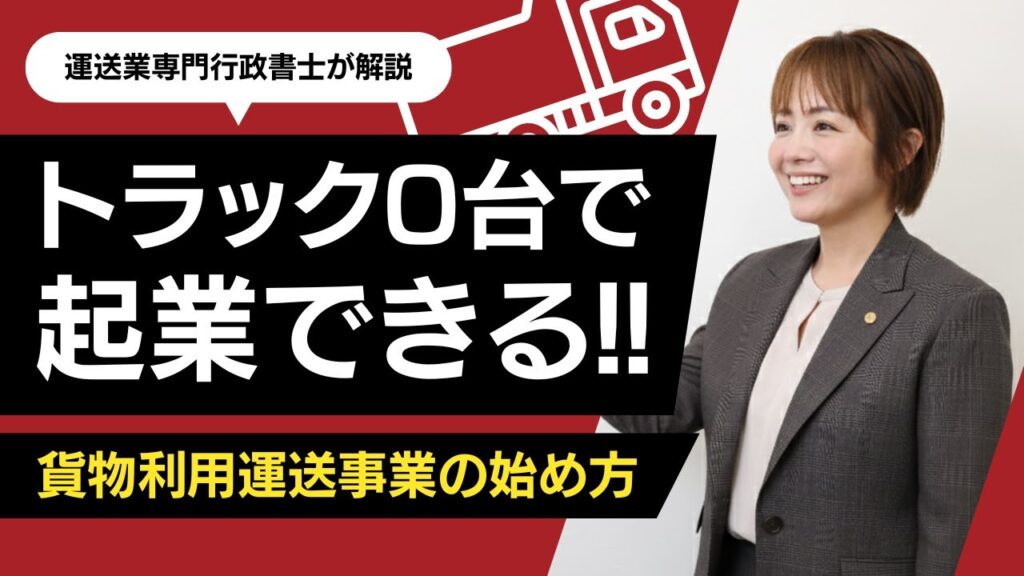
運送業界への参入を検討されている方、または事業拡大を考えている経営者の多くの方が
「運送業を始めるには、トラック5台以上の購入資金、そのための大規模な車庫、そして多数のドライバーの雇用が必要だ」という、
高い初期投資の壁に直面し、挑戦を諦めてしまうのではないでしょうか。
しかし、もしその大きなリスクを負わずに、
あなたの経営手腕とコーディネート能力だけで運送ビジネスに参入できる道があるとしたら、いかがでしょうか?
今回解説するのは、「貨物利用運送事業」、通称「水屋(みずや)」と呼ばれるビジネスモデルです。
貨物利用運送事業(水屋)とは?リスクを抑えた参入の道
貨物利用運送事業とは、一言でいえば「自らはトラックなどの輸送手段を持たずに、他の運送事業者が行う運送を利用して、荷主の貨物を運送する事業」のことを指します。
これは、建設業界で言うところの「元請け」や「ゼネコン」のような立ち位置をイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。
貨物利用運送事業の基本的な仕組み
- 荷主から「この荷物を運んでほしい」という依頼を受けます。
- その輸送業務を、実際に輸送手段(トラック、船舶、鉄道、航空など)を持っている実運送事業者に委託します。
- あなたは、その間に立って輸送全体をコーディネートし、荷主から受け取った運賃と実運送事業者に支払う運賃の差額を利益とします。
最も重いリスク:運送責任はあなたが負うのです
ここで絶対に忘れてはならない、最も重要な点があります。
あなたは単に両者を取り次ぐだけの仲介業者ではありません。この事業であなたは荷主と運送契約を結ぶ当事者となるのです。
これはどういうことか。もし運送中に遅延や荷物の破損といったミスが発生した場合、その責任は、実際に運んだ実運送事業者ではなく、あなた自身が負うということです。
この運送責任を深く理解し、その上で適切な実運送事業者を管理・選定する能力こそが、この事業の核なのです。
引用: 貨物利用運送事業とは、自らは運送手段を保有せず、運送事業者の行う運送を利用して貨物を運送する事業を言います(運送責任を負う)。
なぜ「水屋」が今、注目されるのか?—その最大のメリット
貨物利用運送事業の最大の魅力、それは何といっても事業を始める際の初期費用が圧倒的に低い点にあります。
一般貨物自動車運送事業のように、自社で多額の資金を投じてトラックを購入したり、
広い車庫を借りたり、大量のドライバーを雇用したりする必要がありません。
必要とされるのは、あなたの以下の能力だけです。
- 荷主の輸送ニーズを正確に把握する情報力
- 実運送事業者に適切に運送を手配・管理する高度な調整能力
初期費用を劇的に抑えられるため、事務室についても、ご自宅の一室を事務所として活用することも可能です。ただし、ここで一つ注意が必要です。用途地域(例:第一種・第二種住居専用地域など)によっては事務所の設置が厳しく制限されています。ここは事前に管轄の運輸局や自治体に必ず確認してください。
成功の鍵は「価格」ではなく「信頼」です
「初期費用が安いなら、安さで勝負しよう」と考えてしまうかもしれません。しかし、これは非常に危険な考え方です。
安易な安値競争は、あなたのパートナーである実運送事業者さんの安全性を脅かすことに繋がります。無理な運賃は、ドライバーの労働環境悪化、ひいては重大な事故リスクを高めます。
行政書士として強くお伝えしたいのは、あなたの成功の鍵は「安さ」ではありません。
- 信頼できる実運送事業者を選定する目利き力
- 荷主に対して最適な輸送プランを提案する提案力
- 安全かつ円滑な輸送を実現するコーディネート力
これこそが、あなたの事業価値であり、安定した利益を生み出す源なのです。また、実運送事業者の正常な運営を阻害しないよう配慮することが、法律上も求められています。
引用: 貨物利用運送事業法施行規則第2条第2項では、「貨物利用運送事業者は、実運送事業者の行う事業及び貨物利用運送事業に関連する貨物の流通に関するその他の事業の正常な運営を阻害しないよう配慮しなければならない。」と規定されており、貨物自動車運送事業の制度を理解することが重要となります。
事業開始に必要な手続き—「登録」と「許可」の違い
貨物利用運送事業を始めるためには、運輸局への手続きが必要です。事業の形態によって、比較的簡単な「登録」で済む場合と、ハードルの高い「許可」が必要な場合があります。
1. 第一種貨物利用運送事業(登録)
- 対象: 利用する運送手段が、トラック、鉄道、船舶、航空のいずれか単一である場合。
- 手続き: 運輸局への登録で済みます。
- 要件: 比較的ハードルが低く、例えば、300万円以上の資産があることを証明できれば登録を受けられます。
2. 第二種貨物利用運送事業(許可)
- 対象: 複数の異なる運送手段を組み合わせて輸送をコーディネートする場合(例:船舶や鉄道の利用運送と、それに伴う集荷・配達をトラックで行う複合一貫輸送)。
- 手続き: 国土交通大臣の許可が必要です。
- 要件: 第一種に比べてより厳格な基準が設けられています。
あなたの事業計画がどちらに該当するのか、そしてどのような手続きが必要なのか、
まずは行政書士のような専門家に相談し、確実なスタートを切ることが成功への近道です。
コーディネート能力が未来を拓く
あなたの周りを見渡してみてください。
- 「トラックはたくさんあるのに、仕事がなくて困っている」という運送会社の社長さんはいませんか?
- 「もっと安全で信頼できる運送会社を探している」と悩んでいる荷主さんはいませんか?
貨物利用運送事業とは、まさにこの二つのニーズを見事に繋ぎ合わせるところに、大きなビジネスチャンスが眠っています。
トラック0台から始められるこの事業は、あなたの持つ情報力、調整能力、そして信頼を築く力を最大限に活かせる、運送業の形です。
ぜひ、大きな夢を持って、挑戦の第一歩を踏み出してください。
引用元・参考情報
- 国土交通省. 貨物利用運送事業について (北海道運輸局). https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/jidousya/k_riyou/index.html
- 国土交通省. 第一種貨物利用運送事業者(自動車)の皆様へのお知らせについて. https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk2_000015.html
- 全日本トラック協会. 貨物自動車運送事業法. https://jta.or.jp/member/kaisei_jigyoho/top/jigyoho.html
動画での解説はこちら
執筆:行政書士法人あゆみ 松本 亜由美