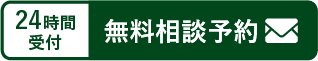運送業で独立したいあなたへ:許可申請で最大ハードルとなる「資金」の壁を乗り越える
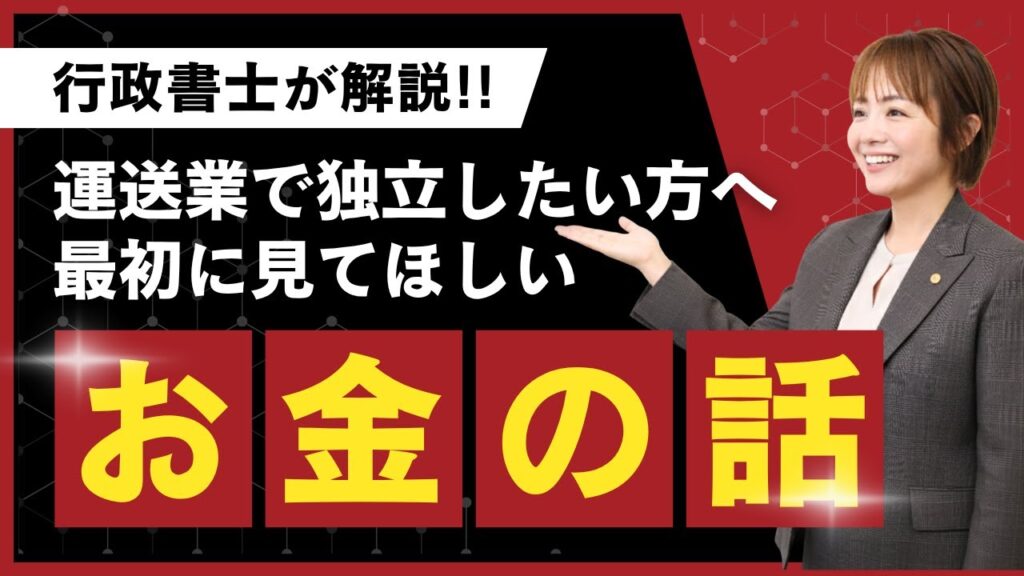
あなたは今、運送業での独立という大きな夢を抱え、その第一歩として許可申請の準備を進めていることでしょう。
しかし、その過程で多くの経営者が直面し、頭を悩ませる最大のハードルこそが、「資金計画」です。
「一体、いくら用意すればいいのか?」
単に銀行口座にお金があれば良いというわけではありません。実は、運送業の許可申請では、その資金の「内訳」と「計画性」が驚くほど厳しく審査されます。
私は、【この資金要件をクリアし、事業を安定的に継続できる裏付けを示すこと】こそが、社会のインフラを担う責任ある仕事である運送業を始めるための第一歩だと考えています。
この資金の壁をクリアできなければ、どれだけ運行管理者や整備管理者を用意しても、事業はスタートできません。
ここでは、専門家として、なぜこの資金要件が重要なのか、そして具体的にいくら、どのように用意すれば良いのかを徹底的に解説します。
なぜそこまで厳しく審査されるのか?(自己資金要件の本質)
運送業は、私たちの生活と経済を支える社会のインフラです。もし事業者が資金不足に陥ればどうなるでしょうか?
- 運転者の給料が支払えなくなり、過労運転を強いる。
- トラックの整備やメンテナンスがおろそかになり、重大事故を引き起こす。
- 結果として、社会的な信用を失い、公共の安全が脅かされます。
だからこそ、許可を出す行政(国土交通省)は、「この事業者は、事業を安定して継続できるだけの経済的基盤を持っているのか」を厳しくチェックするのです。
事業開始に必要な資金のを、申請日から許可になるまでの間、常時確保しておかなければなりません。
— 国土交通省(一般貨物自動車運送事業 新規許可申請における 所要資金及び自己資金の注意点より https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/content/000041156.pdf)
これは、一時的な、申請のための見せかけの資金ではなく、事業を継続するための真の資金力を求めている、ということです。
許可取得に必要な「所要資金」の具体的な内訳
運送業の許可申請で算出する「所要資金」(事業開始に要する資金)は、大きく分けて以下の3つの柱で構成されています。この3つの柱の合計額が、あなたが用意すべき最低限の自己資金となります。
(出典:国土交通省「一般貨物自動車運送事業 経営許可申請書作成の手引」等を参考に構成 https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_saitama/date/3/tebiki.pdf)
1. 事業を動かすための「運転資金」(6ヶ月分)
事業を始めた後、売上が立つまでの間も、下記の費用は発生し続けます。
申請では、安定経営の証として最低6ヶ月分の費用を見込むことが求められます。
- 人件費: 役員報酬や従業員(運転者等)の給料の6ヶ月分。社会保険料も別途加算されます。
- 燃料油脂費: 車両を動かすためのガソリン代やオイル代の6ヶ月分。
- 修繕費: 車両のメンテナンスや修理費として見込む6ヶ月分。
2. 安定経営のための「固定費」(1年間分)
特に高額になりがちなのが、車両と施設に関する費用です。これらは1年分の支払い能力が求められます。
- 車両費:
- 一括購入の場合:取得価格の全額
- 分割購入・リースの場合:頭金+1年分の割賦金(ローン月額)または1年分のリース料
- 建物費(営業所・休憩施設):
- 賃貸の場合:敷金などの初期費用+1年分の賃借料
- 土地費(車庫):
- 賃貸の場合:敷金などの初期費用+1年分の賃借料
- 保険料: 自賠責保険と任意保険の1年分の保険料。特に任意保険は対物200万円以上・対人無制限など十分な補償内容が必要です。
- 各種税金: 自動車税や自動車重量税などの1年分。
3. その他の「一時的な費用」
事業を始めるにあたって一度だけ発生する費用です。
- 登録免許税: 運送業許可が下りた際に国に納付する税金で、一律12万円です。
- その他の経費: 水道光熱費や通信費、消耗品費などの諸経費、おおよそ2ヶ月分を見込みます。
【実例シミュレーション】あなたの事業に必要な資金はいくら?
あなたの事業規模によって必要な資金額はもちろん大きく変動します。
一つの例として、中古の4トン車5台で新規参入するケースを考えてみましょう。
| 項目 | 費用の内訳 | 年間/半年/一回 | 金額(概算例) |
| 車両費 | トラック5台 (頭金+1年ローン) | 1年分 | 410万円 |
| 建物費 | 営業所・車庫の賃料 | 1年分 | 240万円 |
| 人件費 | 社長役員報酬+運転者5名分の給料 | 6ヶ月分 | 1,110万円 |
| 合計 | (概算) | – | 約1,760万円 |
この概算の1,760万円に、燃料費、修繕費、保険料、税金などが加算されるため、実際に許可を取得するまでには2,000万円前後の資金が必要になることが多いのです。
最も重いリスク:見せかけの資金は絶対NG
「こんな大金を全て現金で用意するのは難しい…」
そう考えるのは当然です。金融機関からの正式な融資(日本政策金融公庫や銀行など)を受けて、それを自己資金として計上することは全く問題ありません。事業計画に基づき、返済していくことは立派な経営戦略なのです。
資金確認は二段階なのです
最も重いリスクとなるのは、事業継続の意思がない「一時的な見せかけの資金」です。
- 知人や友人から一時的にお金を借り、残高証明書を取得する。
- 申請が完了した途端に、借りたお金をすぐに返済する。
これでは、許可が下りた後に事業を安定的に継続するための資金が、会社には実質的に存在しないことになります。
なぜ、これが許されないのか? それは、資金計画への向き合い方が、そのまま事業主の誠実さを表すからです。
行政は、許可申請時に一度残高証明書を提出させるだけでなく、許可が下りる直前の「適宜の時点」でもう一度、資金の残高証明を提出するように指示します。
この2回目の確認時点で、所要資金を下回っていた場合、許可は下りません。
これは、事業主が許可が下りるまでの数ヶ月間、その資金を事業のために確保し続けているかを厳しくチェックするためなのです。
運送業は、荷主、運転者、そして社会全体の安全を背負う、責任の重い仕事です。そのスタートラインである資金計画で不正を働くような経営者に、本当に十分な安全を確保し、事業を託すことができるでしょうか。
今一度、ご自身の資金計画が「誠実」かつ「確実」なものであるか、立ち止まってご確認ください。
運送業許可の取得は、経営者としての資質が試される最初のステップです。
許可取得に必要な資金は、決して行政を納得させるための形式的なものではありません。それは、あなたが【従業員を守り、車両を整備し、社会的な責任を果たす】ために必要な「安全への投資」そのものです。
まずは、本日ご紹介した基準に基づき、ご自身の事業計画に必要な総額を計算してみてください。
もし資金調達や資金計画の立て方に少しでも不安があるなら、迷わず私たちのような専門家にご相談ください。
引用元・参考情報
- 国土交通省https://www.mlit.go.jp/
- 一般貨物自動車運送事業 新規許可申請における 所要資金及び自己資金の注意点(自己資金要件に関する引用元)https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/content/000041156.pdf
- 一般貨物自動車運送事業 許可申請の処理方針(許可基準)細部取扱 https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/content/000102178.pdf
- 全日本トラック協会 https://jta.or.jp/
動画での解説はこちら
執筆:行政書士法人あゆみ 松本 亜由美