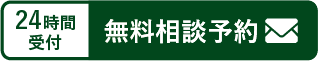「運送業で独立したい…」許可申請でつまずかないために知っておく5つのこと。
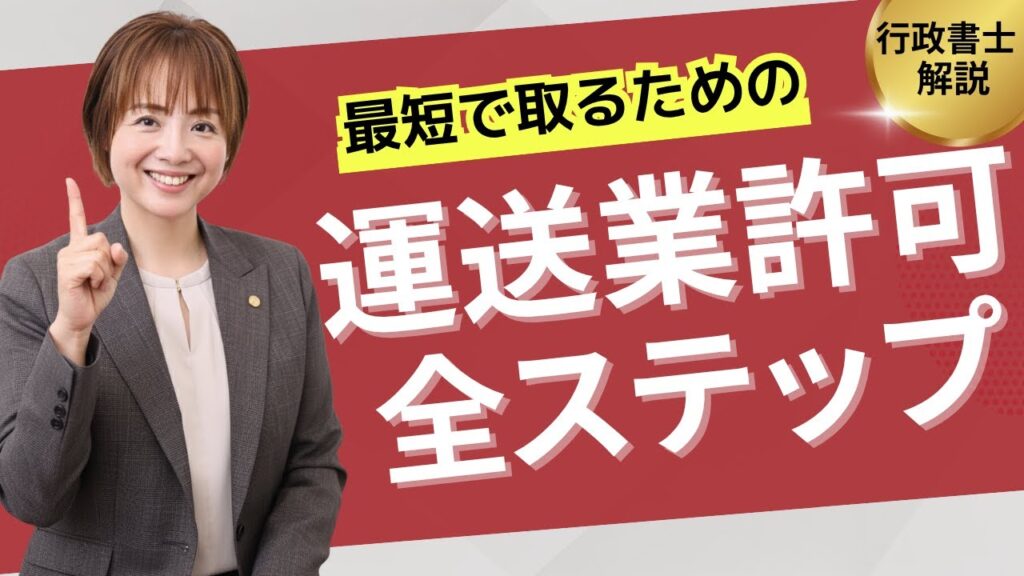
「運送業で独立したい」
その夢を実現するためには、乗り越えなければならない「壁」が存在します。
多くの方が準備不足で時間と費用を無駄にし、最悪の場合、開業の夢そのものを諦めてしまうという悲劇を、何度か見てきました。
運送業の許可申請を単なる手続きではなく、
「なぜこのルールがあるのか」という本質を理解し、最短で確実に許可を取得するための全体像を把握することから始めましょう。
運送業許可の「5つの大きな壁」:なぜそれが必要なのか
一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可を得るには、
国土交通省が定める「輸送の安全」と「事業の継続性」を証明するための厳しい基準をクリアしなければなりません。
これこそが、あなたが最初に立ち向かうべき5つの要件、すなわち「5つの壁」なのです。
これらの要件は、輸送の安全を確保するという、社会的責務を果たすために不可欠なものです。
一つでも欠けたら、絶対に許可はおりません。
1. 「人」に関する要件:安全を担う体制の構築
運送事業の根幹は「人」であり、その安全管理体制が最も重要視されます。
- 運行管理者と整備管理者の確保:
- 車両の日常的な運行を管理する運行管理者(運行管理者資格者証の交付を受けた者が必要)
- 車両の安全な状態を維持する整備管理者(資格者または2年以上の実務経験者)
- 運転者(最低5人以上):
- 事業開始の時点で、常勤の運転者を5名以上確保する必要があります。
この要件の「なぜ」は明確です。 輸送中の事故や過労運転を防ぎ、常に車両をベストな状態に保つ。
そのためのプロフェッショナルな体制を、事業者に義務付けているのです。
なぜ5人なのか? 「事業用自動車の数は、営業所毎に配置する車両が5両以上」と基準で定められているため、これに見合う最低限の運転者数が必要とされます。
2. 「車」に関する要件:最低5台の確保
- 最低車両台数: 5台以上(軽自動車は不可)
- 自己所有でなくても、リース契約でも問題ありません。
この5台という台数要件は絶対です。事業の安定性、そして輸送の安全を確保するための最低限の事業規模を担保しているのです。
3. 「場所」に関する要件:適切な事業基盤
営業所と車庫は、事業活動の拠点です。適当な場所では許可は下りません。
- 営業所と車庫: 農地法、都市計画法などの関係法令に違反していないことが必須です。
- 市街化調整区域の注意点:
- 特に車庫は土地が確保しやすいため市街化調整区域にあることがありますが、この区域は原則として建物の建築が制限されているため、営業所の併設が難しくなるケースが多く見られます。
- 車庫の基準:
- 車両全てが収容できる広さであること。
- 車両の点検・整備のためのスペースが確保できること。
- 前面道路の幅員が、車両の通行に問題ない広さであること。
最も重いリスク:契約前の見落とし
賃貸契約を結んでから、その物件が許可基準を満たせないと判明した場合、お金と時間が無駄になってしまいます。物件契約前に、必ず運送業許可の要件を満たすか行政書士などの専門家へ確認することが、失敗を防ぐ鍵なのです。
4. 「資金」に関する要件:事業継続の経済的基礎
法律は、事業が破綻して安全運行が疎かになることを防ぐため、十分な資金力があるかを求めます。
- 自己資金の証明:
- 車両費、施設費、保険料、税金、そして半年分の運転資金などを合算した「事業の開始に要する資金」を計算し、その全額以上の自己資金が、会社名義の残高証明書で証明されなければなりません。
- 社会保険・労働保険:
- 法令で定められた適切な社会保険への加入は必須です。
資金計画の計算ミスは致命的
自己資金の計算を誤り、残高証明書の金額が不足している場合、許可そのものが絶望的になってしまいます。
この資金計画こそ、正確性と厳密性が求められる最も難しいポイントなのです。
5. 「法令遵守」に関する要件
申請者(法人であれば役員)が、過去に法律違反などで欠格事由に該当していないことが必要です。
安全運行は事業者の「資質」に強く依存するため、過去のコンプライアンス意識が問われるのです。
許可取得から「緑ナンバー」までの全貌:最大の関門とは?
5つの壁をクリアできる見通しが立ったら、いよいよ申請手続きに入ります。しかし、許可申請はゴールではなく、事業開始までの道のりのほんの一部にすぎません。
- 申請書の提出: 運輸局へ申請書を提出します。
- 審査期間: 標準的な審査期間は3ヶ月~4ヶ月程度です(管轄の運輸局により異なります。関東運輸局管轄だと半年から10か月かかることもあるようです。確認を必ず行ってください)。
- 最大の関門:役員法令試験:
審査期間中に、申請会社の常勤役員の方が必ず受験しなければならない試験です。
合格しなければ、他の準備が完璧でも許可は下りません。
出題は、一般貨物自動車運送事業法をはじめとする運送関連法規で、合格基準は出題数の8割以上です。 - 許可の連絡・登録免許税納付:
試験クリア後、運輸局から許可の連絡が入ります。
登録免許税として12万円を納付します。 - 新規事業者向け講習:
管轄の運輸局で行われる講習を受講します。この講習を終えて、ようやく正式な許可書が交付されます。 - 運輸開始前の準備:
許可が下りた後、運行管理者・整備管理者の選任届や、申請書通りに営業所・車庫が整っているかの環境整備を行います。 - 運輸開始前確認:
準備が完了したら、運輸局へ「運輸開始前確認について」という書類を提出します。 - 緑ナンバーへの変更:
運輸局の確認が終わり「連絡書」が発行されて初めて、トラックのナンバープレートを事業用(緑ナンバー)へ変更できるのです。
多くの方が「許可が下りたら終わり」と考えがちですが、実際には、許可取得後の最後の準備と手続き(上記6〜8)こそが、
実際に事業をスムーズにスタートさせるための最も重要な作業なのです。
ここを見落とすと、せっかく許可を取ってもいつまでも事業が始められないという事態になりかねません。
あなたへのメッセージ
運送業の独立・開業は、夢と可能性に満ちたチャレンジです。しかし、そこには安全輸送という重い責任が伴います。
行政書士として強くお伝えしたいのは、書類作成を単なる「穴埋め作業」と侮らないことです。
事業計画書、資金計画書、各種図面など、その数は多岐にわたり、これらを正確に、矛盾なく作成することが、
許可への一番の近道です。特に資金計画のミスは、許可取得の際の致命傷となります。
全体像をを把握し、一歩ずつ着実に進めていきましょうね。
引用元・参考情報
- 国土交通省(中国運輸局):トラック事業を始めるには
- 国土交通省(中国運輸局):許可申請から運輸開始までのスケジュール
本記事の元になった動画はこちら
執筆:行政書士法人あゆみ 松本 亜由美