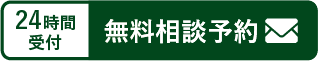【タイヤの脱着作業管理表】たかが「紙切れ」では済まない!運送業の最も重いリスクの車輪脱落事故について

突然ですが、あなたの会社では「タイヤの脱着作業管理表」をきちんと作成し、活用していますか?
「また面倒な紙(管理帳票)が増えただけじゃないか」
そう思ってはいませんか?もしそうなら、それは非常に危険な考えです。
たった一つの車輪の脱落が引き起こすリスクを、私たちは決して軽視してはいけません。
最も重いリスク:重大事故、信用失墜、そして多額の損害賠償
走行中に車輪が脱落すれば、それは即座に重大な人身事故につながり、
一瞬で築き上げてきた会社の信用は失墜します。
さらに、その事故によって生じる損害に対する多額の賠償責任があなた方を襲うのです。
運送業にとって、これほど恐ろしいリスクは他にありません。
この管理表は、単なる記録ではありません。
それは、事故を未然に防ぐための「命綱」であり、会社とドライバーさんを守るための「切り札」なのです。
今日は、なぜこの管理表が事故防止に不可欠なのか、その理由と正しい運用方法を徹底的に解説していきます。
なぜ車輪脱落事故は繰り返されるのか?その複合的な原因
なぜ、どれだけ注意を払っても、毎年車輪脱落事故は後を絶たないのでしょうか。
事故の発生状況を見てみると、ある特定の時期に集中していることが分かります。
それは、冬、特にスタッドレスタイヤへの交換後、1ヶ月以内に多発しているのです。
これは、交換作業が集中することで、どうしてもヒューマンエラーが起きやすくなる時期だからなのです。
しかし、原因はそれだけではありません。私たちは、見落としがちな構造的・技術的な要因にも目を向ける必要があります。
1. 見た目では分からない「整備不良」
ボルトやナットに付着した錆や土埃を清掃せずに締め付けてしまうケースは少なくありません。
トルクレンチで締め付けたとき、「カチッ」という音で規定トルクに達したと安心しますよね。
しかし、その「カチッ」は、本当にボルトとナットが規定の力で締まった音ではなく、
目に見えない摩擦抵抗に打ち勝っただけの音である可能性があるのです。
結果として、走行中の振動であっけなく緩んでしまう、という悲劇が起きてしまうのです。
2. 「JIS」と「ISO」の誤装着リスク
現在の大型車は、ホイールの取り付け方式がJIS方式からISO方式へと変わってきています。
- JIS方式のナット:座面が丸い球面座
- ISO方式のナット:座面が平らな平面座
全く形状が違う部品なのですから、もし間違えて組んでしまうと、面ではなく点でしか接触しません。
これでは、どんなに強く締め付けたところで、走行中のわずかな振動でグラグラになり、脱落するのは当たり前の結果なのです。
事故を防ぐ!整備管理規定に基づく3つのステップ
これらの複雑な要因に対抗し、事故を防ぐために、私たちが具体的に何をチェックすれば良いのか、
その答えは整備管理規定に明確に示されています。
作業は大きく3つのステップに分かれています。
【国土交通省等が推進する「お・と・さ・な・い」のポイント】
車輪脱落事故防止のために、国土交通省や全日本トラック協会などの関係団体は、以下のポイントを掲げています。
「さびたナットは清掃・交換」「なット・ワッシャ隙間に給脂」「とルクレンチで適正締付」
(出典:日本自動車タイヤ協会より、国土交通省・全日本トラック協会と連携した啓発活動「お・と・さ・な・い」のポイント)
この啓発活動の通り、管理表はこの具体的な作業を確実に実施するための道具なのです。
ステップ 1:基本中の基本、清掃と点検
徹底的に清掃することが、事故防止の土台になります。
- ハブやホイールボルト、ナットに付いた錆やゴミを徹底的に取り除く。
- ホイールに亀裂がないか、ナットのワッシャーがスムーズに回るかを細かく点検する。
ステップ 2:油類の塗布(給脂)
清掃と点検が終わったら、油類を塗布します。
- ホイールボルトのねじ部や、ナットとワッシャーの隙間に、エンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布します。
- この作業が、前述した「摩擦抵抗による締め付け不足」を防ぎ、本当に規定トルクで締め付けるための重要な工程なのです。
ステップ 3:取り付けと保守(増し締めを確実に)
最後に取り付けです。
- 規定のトルク値で締め付けを行います。
- そして、ここで終わりではありません。最も重要なのが、走行後の増し締めです。
この一連の流れを、一つひとつ確実に記録し、実行していくことこそが、事故を防ぐ最も確実な方法なのです。
最も重要!2種類の管理表の正しい運用方法
整備管理規定では、役割の異なる2種類の書類を使い分けることになっています。この正しい運用こそが、管理漏れをなくし、安全を担保する鍵を握っています。
1. タイヤ脱着作業管理表(詳細を記録)
これは、1台1台の車に対して、誰が、いつ、どんな作業をしたかを具体的に記録するための書類です。
- 最初のタイヤ交換時、担当した作業員が、清掃・点検・取り付けの状況をこの表に記録します。
- そして、ここからが重要です。その車が50km~100km走行した後、今度は運転手さんなどが増し締めを行い、
- その結果を同じ作業管理表に追記するのです。
- これをもって、1台の車両に対する一連の作業が完了となります。
2. 一覧表(全体を把握)
この一覧表は、全車両の作業状況を把握し、管理漏れを防ぐためのものです。
- 増し締めまで完了した車の情報を一覧表に転記していきます。
- この一覧表を見れば、「まだ増し締めが終わってない車両はないか」「この車両はちゃんと点検したか」といった管理漏れを、整備管理者が瞬時にチェックできるのです。
この2つの管理表を正しく連携させて運用することこそが、冬場の作業集中期に抜け漏れをなくす、最強の体制なのです。
最後に、行政書士としてあなたに伝えたいこと
私たちは、法律や規定というものは、私たちを縛るものではなく、「悲劇を起こさないための知恵」であると理解しなければなりません。
タイヤ脱着・増し締め作業管理表は、単に義務だから作るものではありません。
それは、あなたの会社の存続、ドライバーさんの安全、そして一般の道路利用者の命を守るために、絶対に欠かせない書類なのです。
この管理を徹底することで、あなたは自信を持って「うちの安全管理は万全だ」と胸を張れるようになります。今すぐ、管理表の運用を徹底しましょう。
引用元・参考情報
- 国土交通省:車輪脱落事故 – 自動車の点検整備
- 全日本トラック協会:車輪脱落事故撲滅に向けた取り組み
- 日本自動車タイヤ協会:大型車車輪脱落事故防止に関する情報(「お・と・さ・な・い」のポイントなど)
本記事の元になった動画はこちら
執筆:行政書士法人あゆみ 松本 亜由美