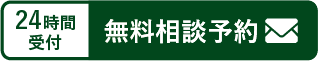物流業界の未来は、ここから変わる!2025年4月施行の物流二法改正を徹底解説

みなさんは「物流二法改正」という言葉を聞いたことがありますか? これは、2025年4月に施行された、日本の物流の未来を大きく左右する重要な法律の改正なのです。
なぜ今、国がこれほどまでに物流にメスを入れようとしているのか、その背景には、深刻な「2024年問題」があります。運転者の労働時間上限規制によって、これまで当たり前だった物流が維持できなくなるかもしれない。日本中の物流が崩壊してしまうかもしれない。そうした危機感から、国はついに重い腰を上げ、長年の課題だった「取引の不透明さ」や「荷主の非協力的な姿勢」を解消するために、この法改正を断行したのです。
運送事業者の武器となる!改正貨物運送事業法の3つのポイント
この法改正は、私たち運送事業者にとって、不利なものではありません。むしろ、これまで不当に扱われてきた部分を正し、正当な対価を得るための強力な「武器」となります。特に重要なポイントは以下の3つです。
1. 契約の書面化が義務に!荷待ち時間にも対価を
これまで曖昧にされてきた、荷待ち時間や積込・積下ろしといった「付帯業務」。これからは、その内容と、それに対する「対価」を明確に契約書に記載することが義務化されます。
「なぜ、これが必要なのでしょうか?」
それは、これまで多くの運送事業者が、荷主の都合で長時間待たされたり、無償で附帯業務を強いられたりしてきたからです。この法改正によって、私たちは「待機料金」や「付帯業務の料金」を正当に請求できる根拠を持つことができるのです。これは、私たちの努力が正しく評価される、大きな一歩なのです。
2. 実運送体制管理簿で「丸投げ」に終止符
下請け、孫請け…と、複雑な下請け構造で、責任の所在が曖昧になっていませんか? 改正法では、誰が実際に運送しているのかを記録する「実運送体制管理簿」の作成と保存が義務付けられます。これにより、元請けの管理責任が厳しく問われることになります。この管理簿は、取引の透明性を高め、健全な業界へと導くための重要なツールなのです。
3. 軽貨物事業者にも規制が!健全な市場へ
軽貨物事業(黒ナンバー)は、これまで運送事業法の対象外でしたが、今回の法改正で、安全管理者の選任や事故報告などの義務が課せられます。 これは、無秩序な市場に一定のルールを設けることで、すべての事業者が安心して、公平にビジネスを行える環境を整備するための措置なのです。
荷主側への変化:協力から「強い努力義務」へ
「運送事業者だけが頑張るのではないか?」と心配している方もいるかもしれません。 ご安心ください。今回の法改正では、荷主側にも大きな変化が求められています。
改正物流効率化法により、荷主は荷待ち時間の削減や積み下ろしの効率化など、運送事業者へ「強い努力義務」として求められます。さらに、企業内での責任体制と責任者が明確になります。これにより、荷主と運送事業者が対等な立場で交渉し、協力し合う関係が構築されていくことが期待されます。
今すぐ始めるべき3つのアクション
この法改正を、ただの「規制強化」と捉えるのではなく、「適正で正当な運賃・料金を収受するチャンス」 と捉えることが重要です。そのために、今すぐ以下の3つのアクションを始めましょう。
- 契約書の見直し: 契約書を全面的に見直し、付帯業務の料金体系などを具体的に確認しましょう。
- 実運送体制管理簿の準備: 国土交通省のウェブサイトでフォーマットが公開されていますので、準備を始めましょう。
- 交渉材料の準備: 荷主との交渉に備え、荷待ち時間のデータなど、具体的な交渉材料を準備しておきましょう。
私たちは、法律という強力な「武器」を手に入れたのです。 このチャンスを活かし、適正な運賃を勝ち取り、健全で持続可能な物流業界を、私たちの手で築いていきましょう!
引用元・参考情報
国土交通省関連情報
- 法改正に関する情報:法改正の詳細や、事業者向けの説明会情報などが掲載されています。(国土交通省 物流効率化法についてより)
全日本トラック協会関連情報
- 「2024年問題」対策:物流の生産性向上や効率化に向けた政府の取り組みが紹介されており、今回の法改正もその一環として位置づけられています。(全日本トラック協会 2024年問題特設ページより)
この動画も合わせてご覧ください
このブログ記事は、以下の動画を参考に執筆しました。 動画ではさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
執筆:行政書士法人あゆみ 松本 亜由美