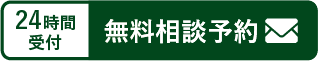【2025年最新版】Gマーク加点評価の鍵を握る3つのポイント

「よし、うちもGマークを取得するぞ!」と決意したものの、いざ準備を始めると「一体何から手をつければいいんだろう…」と悩んでいませんか?Gマークの審査は、安全への様々な取り組みを点数化し、その合計点で合否が決まります。ただ闇雲に頑張るのではなく、審査で評価される加点ポイントを効率的に押さえていくことが非常に大切です。
この記事では、2025年度の全日本トラック協会の評価項目に基づき、Gマークの加点評価で特に重要となる3つのポイントを、専門家の視点から分かりやすく解説します。
ポイント1:ドライバーの教育と情報共有を徹底する
Gマーク評価の大きな柱となるのが、ドライバーさんたちへの安全教育です。特に、2025年度からは研修で得た知識を全ドライバーに情報共有する仕組みが評価項目に追加されました。
なぜ、情報共有がそこまで重要なのでしょうか?
それは、研修に参加できたドライバーと、そうでないドライバーとの間に情報の格差が生まれるからです。この情報格差を放置すると、安全に対する意識のムラが生じ、重大な事故につながるリスクを高めてしまうのです。
Gマークの加点対象となるために、以下の項目をチェックしてみてください。
- KYTやドライブレコーダー映像の分析など、独自の安全教育を定期的に実施していますか?
- 全日本トラック協会などが主催する外部の安全講習会にドライバーを派遣していますか?
- 自動車安全運転センターの運転記録証明書を取得し、違反歴のあるドライバーに個別指導を行っていますか?
- 会議や研修に参加できなかったドライバーにも、内容を資料などで確実に共有し、サイン付きの記録を残していますか?
これらの取り組みを行った際は、必ず日付・参加者・内容が分かる客観的な資料をセットで保管しておきましょう。これが加点評価に直結する重要な証拠となります。
ポイント2:デジタコを徹底活用する
「うちのトラックにはデジタコ全車ついているから大丈夫!」と思っていませんか?実は、単に機器を導入しているだけでは不十分で、その機器から得られたデータをどうやって安全指導に生かしているかがGマークでは問われます。
なぜなら、機器はあくまでツールであり、そのデータを活用してドライバーの行動を改善しなければ、本当の安全にはつながらないからです。
- デジタコの運行データを分析し、速度超過や急ブレーキが多いドライバーに個別指導を行っていますか?
- 急発進や急加速の状況をデータで示し、省エネ運転の指導をしていますか?
これらの具体的なサイクルを指導記録としてきちんと残しておくことが、加点ポイントに繋がります。
ポイント3:手厚い健康管理でドライバーを守る
Gマークの審査では、会社としてドライバーさんの健康に対する取り組みが非常に重視されます。法定基準を上回る手厚い健康管理が加点対象になります。
運送業において、ドライバーの健康は会社の安全を左右する最も重要な要素です。ドライバーが体調不良を抱えたまま運転を続ければ、自分だけでなく、他の人命を危険に晒すことになります。
- 健康診断で「要再検査」となったドライバーに対し、再受診を促すなどのフォローアップをしていますか?
- 脳ドックや睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニング検査を会社として実施していますか?
こうした具体的な取り組みこそ、ドライバーさんを守り、ひいては会社の安全を守ることに繋がります。
まとめ
Gマーク取得のための加点項目は、以下の3つに集約されます。
- ドライバーの教育と情報共有
- 安全機器の徹底活用
- 手厚い健康管理
これらの項目は、Gマーク取得のためだけに慌ててやるものではありません。これらは自社の安全管理体制を見直す絶好の機会と捉えることが大切なのです。日々の安全管理をしっかり行い、その延長線上にGマークがある。この考え方こそが、Gマーク取得の最も大切な心構えです。
Gマーク取得は、会社としての安全意識の高さを示し、荷主さんや社会からの信頼を獲得するための重要なステップです。ぜひ、この機会に自社の安全管理体制を見つめ直し、安全な運送事業の実現を目指してください。
ご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
引用元・参考情報
- 全日本トラック協会「安全性優良事業所(Gマーク)制度」
https://jta.or.jp/member/tekiseika/gmark.html
本記事の元になった動画はこちら
本記事の内容は、YouTubeチャンネル「あゆみのうんそうラボ」の以下の動画を参考に執筆しました。
執筆:行政書士法人あゆみ 松本 亜由美