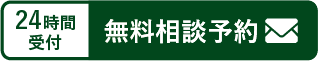【運送事業者向け】アルコール検知器で0.15mg/l道交法OKでも貨物自動車運送事業輸送安全規則ではNG!なぜか?
「なぜ道路交通法ではOKなのに、我々はアルコールが少しでも検知されたらダメなのか?」
という質問を何度か受けたことがあります。
この記事では、この質問について解説していきたいと思います。
これは、決して「運送会社を厳しく締め付けようとしている」意地悪なルールなどではありません。
事業者が法律で義務付けられている、絶対に守るべきものであり、
会社のコンプライアンス、そしてリスクマネジメントそのものなのです。
1. 2つの法律、2つの役割。その違いとは?
法律には、それぞれ目的が違います。
この違いを理解すれば、一見矛盾しているように見える「2つの基準」の理由が明らかになります。
【道路交通法】
これは、日本国内で運転するすべての人が守るべき法律です。
目的は、飲酒運転による事故を防ぎ、すべての道路利用者の安全を確保することにあります。
対象: 乗用車を運転する一般ドライバーを含む、すべての運転者。
基準: 呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上の場合に罰則の対象となります。
役割: 国が定める最低限のボーダーラインです。
いわば、「これ以上飲むと、運転は危険ですよ!」という危険防止のルールです。
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
次に、事業用自動車(緑ナンバー)を扱う事業者が守るべき法律です。
対象: 運送事業者および、その事業に従事するプロドライバー。
基準: アルコールがわずかでも検知されたら乗務はNG。数値の大小は一切関係ありません。
役割: こちらの法律の目的は、公共の安全を最大限に確保することにあります。
事業用車両は、多くの人々の命や社会経済を支える荷物を預かっており、
ひとたび事故を起こせば、その社会的影響は甚大です。そのため、プロにはリスクをゼロに近づけることが求められています。
この二つの基準は、「一般人」と「プロ」の役割の違いを明確に示しています。
2. なぜ「ゼロ」が義務なのか?見過ごせないリスク
最も重いリスク:人命の喪失
飲酒運転がもたらす最も重いリスクは、人命の喪失です。
わずかなアルコールが、運転手の判断力や集中力を鈍らせ、一瞬の不注意で、まったく無関係な人のかけがえのない命を奪うことになります。
一度失われた命は、二度と戻りません。
事故で命を落とした被害者のご家族が背負う、決して癒えることのない悲しみ。
加害者となったドライバーが一生背負う、拭い去ることのできない罪の意識。
これは、会社の事業停止や莫大な賠償金といった経済的な損失をはるかに超える、取り返しのつかない悲劇です。
社長・事業者は、この事実を最も重いリスクとして、全従業員に徹底して伝える責任があります。
「飲酒運転は、他人の人生だけでなく、自分自身の人生も破壊する」
この一点を、決して忘れてはならないのです。
行政処分のリスク
飲酒運転が発覚した場合、事業者は厳しい行政処分の対象となります。
事業停止: 飲酒運転は、法令違反の中でも特に悪質とみなされます。
運行管理者資格の返納や、営業所全体の事業停止命令が下される可能性があります。
車両の使用停止: 車両が使用停止となり、運行計画が滞ることで、会社全体の業務に深刻な影響を及ぼします。
これらの処分は、会社の売上を途絶えさせ、従業員の生活を脅かす、事業存続に関わる致命的なリスクです。
社会的信用の失墜
飲酒運転による事故は、ニュースで大々的に報道されます。
「〇〇運送のドライバーが飲酒運転で事故」という報道は、長年かけて築き上げてきたお客様や取引先からの信用を、一夜にして崩壊させます。
一度失った信頼を取り戻すことは極めて困難であり、新規顧客の開拓も難航します。これは、企業のブランド価値を根底から揺るがす、最も恐ろしいリスクです。
莫大な経済的損失
飲酒運転が原因で事故が発生した場合、会社は使用者責任として、莫大な損害賠償を請求される可能性があります。
事故の規模によっては、会社の財務状況を完全に破壊するほどの金額に上ることもあります。さらに、事業停止期間中の売上損失や、信用回復など、目に見えないコストも膨大です。
3. アルコールチェックは「会社の未来を守る」投資
厳格な飲酒運転対策は、単なる義務や負担ではありません。それは、会社を成長させるための未来への投資です。
コンプライアンスの強化: 法令を厳格に遵守する企業として、社会的な評価が高まり、他の企業との取引においても優位に立てます。
安全な職場環境の構築: 飲酒運転というリスクが排除されることで、従業員は安心して業務に集中できます。
「この会社は、社員の安全を第一に考えてくれている」という信頼感は、社員・運転手のモチベーションや定着率向上に繋がります。
ブランド価値の向上: 徹底した飲酒運転対策は、お客様からの信頼をさらに厚くし、会社のブランド価値を高めることに繋がります。
結論:「なぜ0.15mg/L以下でもダメなのか?」
この問いへの答えは、
「プロである私たちにとって、アルコールはゼロでなければならない」からです。
アルコールチェックは、単なる義務ではありません。
それは、自分自身の命を守り、会社の信用を守り、そして社会の安全を守るための、最も重要な責任確認です。
厳しい基準を徹底することは、決して窮屈なことではありません。
それは、私たちが「安全と信頼を運ぶプロ」であることの証明であり、会社の成長を確実にするための重要な経営判断なのです。
執筆:行政書士法人あゆみ 松本 亜由美